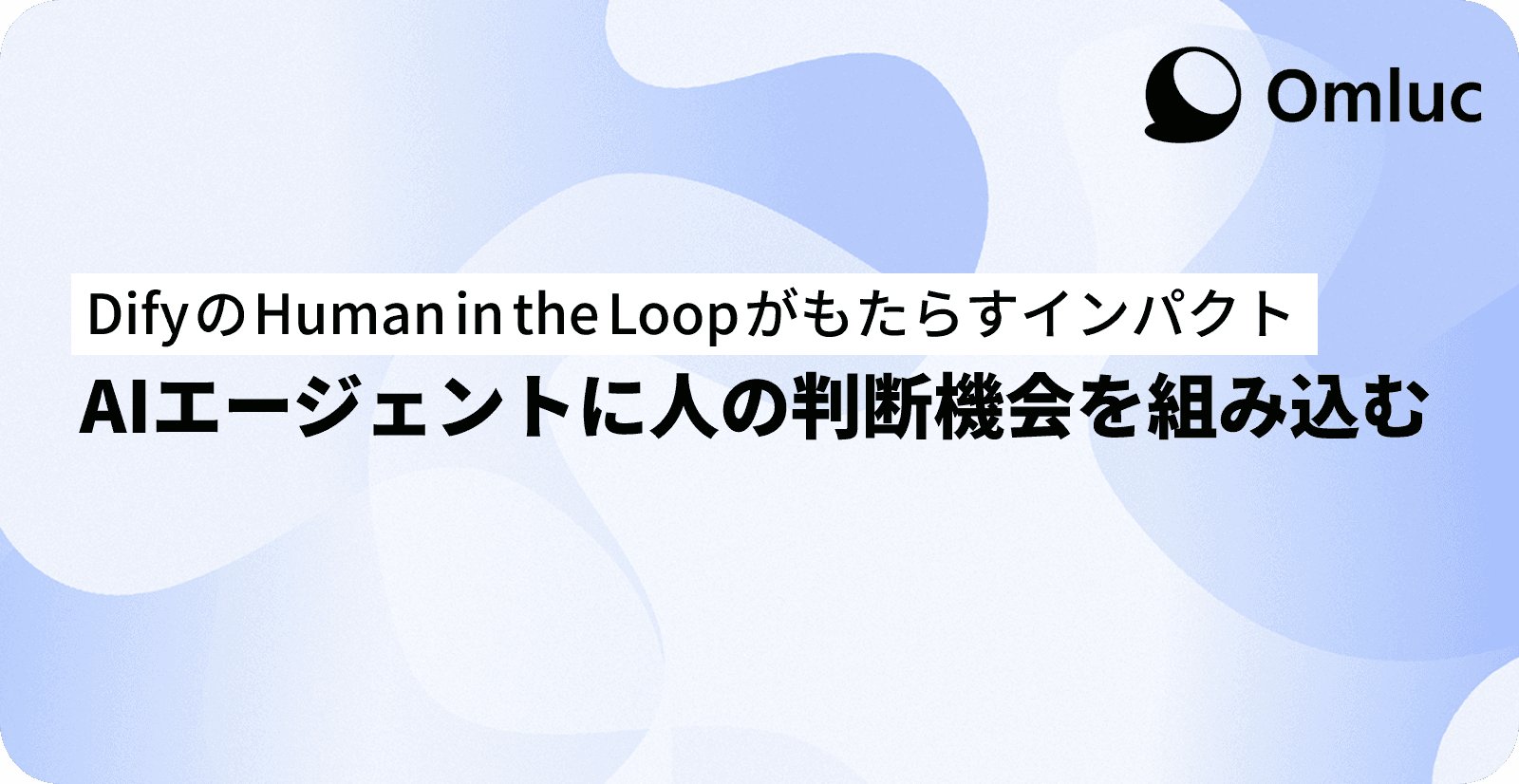Dynabook社のソリューション事業を支えるOmluc ~ Dynabook × Omlucが描く、生成AI時代の現実解とDifyの可能性 Part1
コラム
2026/02/17
生成AIは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、能力と応用面の進化が加速度的に進んでいる状況です。一方で、多くの企業が「試したが業務に定着しない」「PoCで止まっている」という壁に直面しているのも事実で、そこから抜け出せずにいる企業は少なくありません。
そうした状況で、ハードウェアを起点に、生成AIを“業務の現場に実装する" という独自のアプローチを進めているのがDynabook株式会社です。
本対談Part1では、Dynabookでソリューション事業を牽引する麻生氏・宮入氏と、Difyを中心に企業向け生成AI導入支援を行うOmluc代表 岸田が、約1年にわたる両社の協業を振り返りながら、
なぜDifyとOmlucを選んだのか?
なぜ「オンプレミス×ローカル生成AI」という選択をしたのか?
生成AI活用が“ツール選定”ではなく“業務理解”のフェーズに入っている理由
について語り合いました。
Dynabookが生成AIに本気で取り組む理由
岸田(Omluc)
もう1年ほどご一緒していますが、まずはあらためて、Dynabook社が今どのような位置づけで生成AI事業に取り組まれているのかを伺えればと思います。
麻生氏(Dynabook)

DynabookというとノートPCメーカーというイメージが強いと思いますが、私たちはソリューション事業本部という部門に所属しています。ドラレコを活用した運行管理や安全運転支援、XRデバイスなど、付加価値創造型のハードウェアを起点にしたソリューションビジネスを以前から展開してきました。
その流れの中で、約1年前から本格的に生成AIに取り組み始めました。ちょうど企業側でも「生成AIをどう業務に使うか」を真剣に考え始めた時期だったと思いますし、実際、お客様からの相談も増えていました。
Dynabookの強みは、ハードウェアの知見、GPUなどの調達力、全国をカバーする販売網とサポート体制です。この強みを活かしながら、生成AIを単なるツールではなく「業務を変える仕組み」として提供できないか。それが出発点でした。
Difyを通じて出会ったOmlucの「AIへの熱意と意志の強さ」
お客様に提供するDynabookのソリューションとして生成AIの活用基盤を調査検討する中で、麻生氏が注目したのがDifyでした。
麻生氏
いろいろと調査を進める中でDifyを知り、「これならお客様自身がAIアプリを作れる」と感じました。お客様自身がAIを“使う側”から“作る側”に回れる。ワークフローを組むだけで業務に即したAIアプリが作れる。しかもオープンソースでオンプレミスでも動かせる。
そこで、我々が提供するワークステーションとDifyを利用した生成AI環境を組み合わせれば、セキュアで実用的な生成AI基盤になると、そしてこの組み合わせはDynabookならではのお客様への提供価値になると考えました。
ただし、課題も明確でした。Difyは「使いこなせば強力」ですが、最初の設計と構築・運用方法・生成AIの効果的な使い方には専門知識が必要です。
Dynabookは、ハードウェアの知見は豊富ですが、この分野についてはさらに専門性を強化したいと考えていました。そこで、一緒に取り組むパートナーを探す中でOmluc社に出会ったのがちょうど1年前の話です。
私が必要だと感じていた「Difyの研修・導入支援・技術支援」がすべて揃っていて、しかも生成AIやアーキテクチャの深いところまで理解している。そのような知見の豊富さに加えて、AIへの強烈な熱意も感じて直感的に「Omlucしかない」と思ったのを覚えています。
ローカル生成AIという選択肢が持つ意味
岸田
Dynabook社のAIソリューションのアプローチで特徴的なのが、オンプレミスとローカルAIを前提にしている点ですよね?
麻生氏
はい。理由は明確で、セキュリティとコントロール性です。クラウドAIは便利ですが、アップデートのタイミングやデータの扱いを完全にコントロールできないケースもあります。オンプレミスとローカルAIの組み合わせであれば、
機密データを外部に出さない
勝手に生成AIモデルや挙動が変わらない
導入コストも抑えやすい
というメリットがあります。AIサーバーほど高額な投資が不要なAIワークステーションを生成AI活用基盤として提供するのは、まさにDynabookの得意領域です。
宮入氏(Dynabook)

GPUなどの調達が厳しい時期もありますが、そこはハードメーカーとしての調達力が活かせる部分になります。今後、生成AI需要はますます高まると予想されるので、この強みはさらに重要になると感じています。
「ツール選び」から「業務理解」へ
対談を通じて繰り返し語られたのが、生成AI活用のフェーズ変化です。
岸田
最近は「DifyとCopilot、どちらが良いか」と聞かれることが多いですが、比較自体が本質ではないと感じています。
宮入氏
同感です。Difyは特定業務に深く入り込み、業務そのものを置き換えるためのツール。一方でMicrosoft 365 Copilotは、横断的に業務を支援するツール。用途がまったく異なります。
麻生氏
結局、お客様の課題をどこまで理解できるかが重要です。「AIを使いたい」ではなく、「どの業務を、どう変えたいのか」。そこを一緒に考えられる体制がなければ、生成AIは定着しません。
Dynabookでは、営業とSEが連携し、より上流から業務を理解する体制づくりを進めています。その中で、Difyの自由度の高さやカスタマイズ力が活きてくると感じています。
Omlucとの協業が生む価値
麻生氏
Difyはノーコードで使う人が多いと思いますが、使い続けると必ず「次のレベル」に行きたくなる。そのときに、Difyの中身や生成AIモデルの挙動まで理解しているOmluc社が後ろにいるのは非常に心強いです。
岸田
Omlucとしても、単なるツール導入ではなく、「何を実装したか」「どんな業務価値を出したか」そこまでをお客様と一緒に考えることを大切にしています。
フルスクラッチ開発の知見を持ったエンジニアが、Difyを“高速に価値を作る道具”として使う。このスタイルが、これからの生成AI活用の現実解だと思っています。
生成AIが「当たり前の業務スキル」になる未来へ
麻生氏
将来的には、ExcelやWordのように「自分でAIアプリを作れる」ことが当たり前のスキルになるかもしれません。Difyには、そうした未来を感じています。
岸田
だからこそ、今年はより具体的な活用事例を増やしていきたいですね。抽象論ではなく、「この業務で、こう使って、こう変わった」という話を。
Dynabook社の現場力と、Omlucの生成AI実装力。この組み合わせで、生成AIを“使える技術”から“成果の出る仕組み”へ進化させていければと思っています。
生成AI活用は、もはや「最新技術の導入」ではなく、業務変革の手段へとフェーズが移りつつあります。Dynabook社とOmlucの協業は、その現実的な一歩を示す好例と言えるでしょう。
Part2へ続く